サステナビリティ
Sustainability
Sustainability
社会
当社ではステークホルダーを意識したESG経営を推進しています。
お客様やお取引先、従業員に対する取り組みをご紹介します。
当社は、グループ経営理念体系の中の5つの指針の第一に「こころに残るおもてなし」を掲げています。これはお客様の立場になって考え、お客様の心に確実に届くおもてなしを実践していくことを表していますが、これらのベースになるのが、お客様の安全・安心への取り組みです。
お客様の声を反映した品揃えやご要望にお応えするためのサービス面の向上はもちろん、デジタル技術を活用した新しい商品提案や、ご購入いただく商品における品質管理の徹底などに取り組んでいます。
2025年6月にタカシマヤアプリをリニューアルしました。アプリの会員登録を必須化することでお客様への理解を深め、お客様にとって魅力的なサービスを拡充していきます。その第1弾として、バースデーなどアプリ限定クーポンや、期間限定イベントを即座にチェックできる機能「今日の高島屋」、お客様の興味関心カテゴリーごとのメッセージ送り分けなど、さまざまな新しい仕組みをリリースしました。
今後もアプリの改修を段階的に進めながら、次世代を担う若年層やインバウンドのお客様にもご利用いただきやすい環境を整え、将来にわたる安定的な顧客基盤の構築につなげていきます。同時に自社クレジットカード顧客とのID連携により、長く当社グループをご愛顧いただいているお客様への特典も更に充実させることで、アプリを軸として持続的なLTV(Life Time Value= 顧客生涯価値)向上とシームレスなお買物環境の創出に向けた取り組みを進めていきます。

日頃からお客様の声をもとに品揃えやサービスの改善を行っています。従業員が店頭でおうかがいしたご意見を登録する「ウォントスリップ」、お客様ご自身でご記入いただく「ローズちゃんハートシート」やお電話、お手紙、メールなどでお寄せいただくお声はすべてデータベース化し、全社で共有しています。そして、これをもとに品揃えやサービスの改善に取り組んでいます。「お買物する楽しみ」をお客様に提供できるよう、「セールススペシャリスト」や「ストアコンシェルジュ」の配置も実施しています。
当社のセールススペシャリストは、「シューフィッター」や「フィッティングアドバイザー」「ベビーコンサルタント」など、公的資格や髙島屋独自の社内資格を取得しており、その分野において、より専門的な知識を持った販売員がお客様のお買物をお手伝いします。
また、現在、大阪店・日本橋店・横浜店・新宿店・玉川店に配置しているストアコンシェルジュは、セールススペシャリストなどとも連携しながら、全館の商品をコンサルティング。お客様の生活全般に寄り添い、より高度な商品提案を実現しています。
「お客様に信頼される安全・安心な商品の販売・提供」に向け、東西に検査室を設け専任スタッフを配置。また、各店・事業部にも専門スタッフをそれぞれ配置しています。
品質管理グループでは「情報発信」「指導啓発」「検査・調査」「危機管理対応」などの機能を発揮するべく、百貨店として多品種の商品に対応するために、髙島屋グループの自主基準(品質管理基準・表示管理基準)を整備しています。
新しいお取引先と取引を始める際には、事前に製造プロセスや品質管理体制のチェックを行い、確実な商品の販売に向けた助言・協力要請を行っています。さらに、近年は食料品におけるHACCP対応など、より細かな対応が必要となる中、お取引先への説明会や資料提供を適宜実施し、お取引先とともに、安全・安心な商品の販売・提供に向けて取り組みを進めています。
また、検査には商品を壊さずに迅速な検査が可能なスクリーニング機器(蛍光X線分析装置)やマイクロスコープなどを活用し、正確な検査を行い、わかりやすい検査結果報告書を作成するなど、商品の安全性や品質の確保に努めています。
当社は「すべての人々が21世紀の豊かさを実感できる社会の実現」に貢献していくことを目指し、生産・製造・流通の一連の取引において、法令遵守はもとより、幅広い視点で社会的責任に基づいた取引を推進しています。
当社の営業を支えていただいている大事なパートナーである全てのお取引先の皆様と公平で良好なパートナーシップを築きながら、よりよい取引を継続的に推進し、共存共栄を図っていきます。
事業活動における一連の取引において、法令遵守はもちろんのこと、環境保全や人権などに配慮し、公正・公平な取引を推進することを目的として、2024年1月、「高島屋取引指針」を改訂し、「高島屋グループ取引指針」として策定いたしました。
この指針の実行には、お取引先の皆様のご理解・ご協力が不可欠です。お取引先の皆様と共に、サプライチェーン全体で取り組みを推進してまいります。
良きパートナーとしてお取引先とよりよい関係を築くには、相手を敬い、十分なコミュニケーションと相互理解を図ることが重要です。当社の利益のみを優先することなく、お取引先と事前に十分に話し合ったうえで取引条件を取り決め、これを明確にするために書面化しています。
そして最も重要なことは、合意内容を確実・誠実に守ることです。各種マニュアルや取引内容を明確化する書面類を活用し、公正・適正な取引を推進しています。
「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを宣言するものです。
当社においても事業活動に関わる全てのお取引先と公平なパートナーシップを築き、共存共栄を図っていくことを目指しており、「パートナーシップ構築宣言」の趣旨に賛同し、参画いたしました。
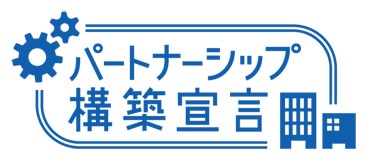
グループ経営理念「いつも、人から。」のもと、「人」を最も重要な経営資源ととらえ、一人ひとりの「個性」と「意欲」を組織の成長につなげることを目指しています。一人ひとりが働きがいを感じ、自らの目標に向けて主体的に努力をする組織づくりのため、従業員の自主性を最大限に引き出す人事制度や豊富な研修メニューを整備しています。
また、コンプライアンスやハラスメント相談などさまざまな相談窓口の設置や、生産性向上を目指す「SAY活動」をはじめ、労使関係に基づく活動など、髙島屋グループで働くすべての従業員が安心して働ける環境整備に取り組んでいます。
なお、詳細につきましては、「人的資本経営の推進」ページをご覧ください。