サステナビリティ
Sustainability
Sustainability
社会
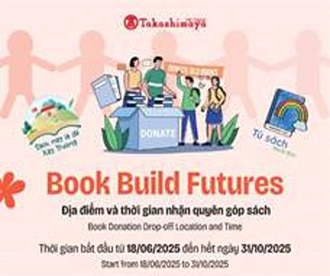
ホーチミン高島屋では、ベトナムの遠隔地の恵まれない子どもたちの識字能力向上や教育支援改善をめざし、2025年6月から10月までの期間を第1フェーズとして、従業員から不要となった本の回収を始めました。(7月末時点で236冊を回収。)最も評判の高いNGOの1つであるNuôi Em (Raise the Child) と協力し、回収した本を寄付することで、村や学校に「ミニ図書館」を設置するための継続的な支援活動を行っています。

ホーチミン高島屋では、地域との交流深める取り組みとして、24年11月にホーチミンの日本人小学校2年生90名を受け入れ、お仕事体験を実施しました。各班に分かれて、普段は見ることができない「高島屋の舞台裏」を体験いただきました。顧客チームでは開店時の迎客や包装体験を通して、高島屋ならではの丁寧なサービスを体験、食料品チームではパン作りや商品の陳列体験を通して、普段購入する商品の裏側について学習いただきました。また、従業員へのインタビューを通して、高島屋や仕事に対する理解を深めていただき、生徒さんからは「今度は家族で高島屋に行きます」といった温かいお言葉をいただきました。


名古屋市身体障碍者福祉連合会に所属する障がい者が、企画、デザイン、裁断、縫製から販売までを担っている「Nagoya Bags」のタイでの販売を支援しています。特に、「招き猫」のデザインはタイでも大変人気です。また、これらの商品は、名古屋市消防局で使用済みとなった消防服(アラミド繊維製の防火服)や鉄道制服を回収し、それを素材にバッグを制作しているため、廃棄衣料のアップサイクルによって廃棄物の削減につながっています。
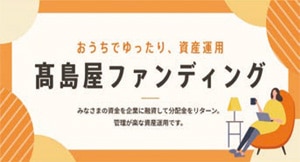
高島屋ファイナンシャル・パートナーズでは、日本橋店・横浜店・大阪店のタカシマヤ ファイナンシャルカウンターで、お客様の資産形成・万一の保障・相続などに関する相談を金融商品・サービスを通じて解決する事業を展開しています。我が国においては、超高齢社会への国民の備えの必要性や社会において家計金融資産が活かされていない等の背景から、2024年からの新NISA制度など資産運用立国の政策・取り組みが推進されていますが、社会全体としては基礎的な金融知識の不足や家計金融資産の半分以上を現預金が占めるといった状況に留まっています。高島屋ファイナンシャル・パートナーズでは、お客様と社会をつなぐプラットフォームとなるべく、百貨店の店頭にあるお客様にとって広く身近な存在としてタカシマヤ ファイナンシャルカウンターを運営し、当社アドバイザーによる最適なアドバイス・提案を通じたお客様の安定的な資産運用への貢献によって、本業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。また、高島屋ファイナンシャル・パートナーズでは、「資金調達をしたい企業」と「お金を貸して利回りを得たい投資家」を結ぶソーシャルレンディング(別名:貸付型クラウドファンディング)事業を2021年7月に開始し、累計13件(2024年10月時点)の案件を実施しています。事業者の資金調達ニーズとお客様の資産形成ニーズに応え、双方の橋渡し役を担い、融資を通じた社会
貢献を進めています。
高島屋では2024年6月、社会課題の解決をめざす非営利法人や研究機関へ必要な資金を届ける仕組み「FUKUWAKE」を構築し、ウェルス・マネジメントと社会貢献活動の融合を進めることで、より良い社会の実現をめざしているヴァスト・キュルチュール株式会社を子会社化しました。今後も、高島屋ファイナンシャル・パートナーズを中心に、高島屋グループとして金融ビジネスを通じた社会課題解決に貢献していきます。
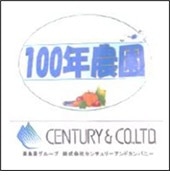

センチュリーアンドカンパニーでは、障がいのある方が楽しく、やりがいを持って働ける環境を提供する㈱エスプールプラスが運営する企業向け貸し農園(わーくはぴねす農園市原ファーム)に参画しています。農園を『100年農園』と名付け、障がい者就業支援の一環として2013年からスタートし、農園長1名と契約社員3名が就業しています。『100年農園』のネーミングは、社内公募によるもので農園を長く継続させていきたいという農園勤務者の思いと社名の“センチュリー”=1世紀(100年)のイメージが重なり決定しました。就業者が作物を育てることで責任感や、やりがい収穫できた喜びを感じることに繋がっています。
2025年度は2名の新入社員が、農園のメンバーと共に野菜作りを体験しました。本人たちからは、この体験を通じて「一人ひとりの能力や特性を生かして活躍されている姿を拝見し、障がい者雇用の社会的意義について改めて考える貴重な機会となった」「農園では得意不得意をそれぞれのメンバーが補い合いながら能力を発揮されていて、とても明るく賑やかな環境で体験できた」といった感想が寄せられ、障がい者就業支援の社会的意義や、職場の多様性について理解を深める有益な時間となりました。