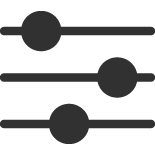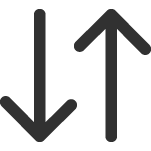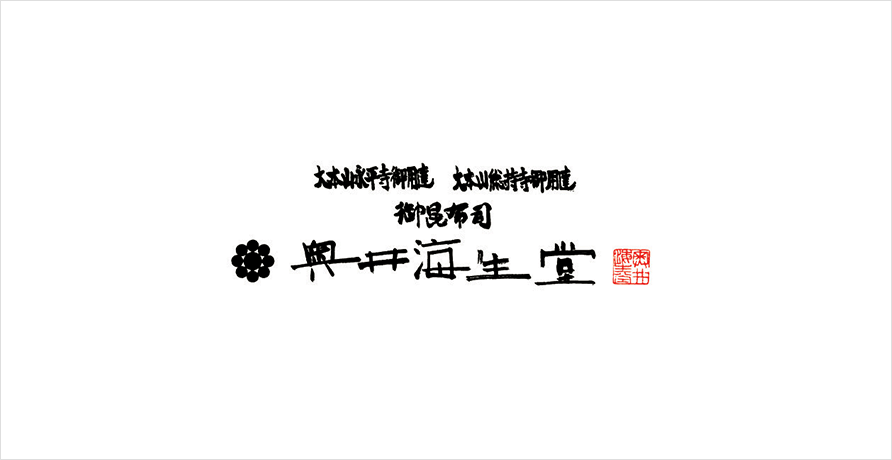
奥井海生堂
敦賀の風土が育んだ,料理人を魅了する「蔵囲(くらがこい)昆布」。
もっと見る曹洞宗大本山永平寺御用達を司る日本屈指の昆布商。
敦賀で暖簾を守り、上質なだし昆布を謹製。
1871(明治四)年創業の「奥井海生堂」。交通の発達により消えかかった「蔵囲」の手法を、近代的な専用蔵によって継承し、上質なだし昆布の老舗として、料理人たちにもその名を馳せています。
江戸時代から明治時代の中頃まで、昆布が日本海航路で西へ運ばれる際の玄関口として栄えた港町、福井県敦賀。夏に収穫し、天日干しされた北海道の新昆布は、晩秋の頃、この地に荷揚げされました。雪深い北陸では冬に荷を運べず、昆布は敦賀の蔵でそのまま越冬します。春になり出荷の前に味わうと、新昆布の荒々しさや雑味が消え、旨みが際立つ品に変化していました。昆布を蔵に寝かせ、味を深める。敦賀に伝わる「蔵囲」という手法はこうして誕生したといわれています。
温湿度の安定した専用蔵で旨みが磨かれる。
産地で収穫してすぐに天日で乾燥させた利尻昆布を1年以上寝かせ、旨みに磨きをかける「奥井海生堂」の蔵囲昆布。梅雨時も温度や湿度を自動調整できる昆布専用蔵は、常に湿度60%前後、温度20~22度に保たれています。
豊かな環境で育った昆布は、熟成を経て雑味のない仕上がりに。
最高級と称される利尻昆布をわらで編んだムシロで覆い、長期熟成。熟成が深まるにつれ、旨みが増し、昆布独特の磯臭さや雑味が抜けていき、透明でクセのない、上品なダシがひける芳醇な香りや風味が醸成されます。現当主4代目社長・奥井隆さんは「ひんやりした蔵内で、昆布は呼吸しています」そして「温度、湿度、光を管理し、ワインのように熟成していくのを見守ります」と言います。奥井海生堂の昆布は、こうして、大自然が育てた食材を時間と人の手技で仕上げられています。

RANKING カテゴリ別ランキング
奥井海生堂/味百選
【よりどり】おぼろ昆布
税込842円
敦賀の風土が育んだ「蔵囲い昆布」は、料理人を魅了する逸品。職人が一気に削り込む手漉きおぼろ昆布はうま味と香りが格別です。淡く溶けるような白色、口に入れればうま味が一杯にひろがります。
2件 (1/1ページ)
2件 (1/1ページ)

表示切り替え
件数表示