![]() MANNERS
MANNERS
高島屋のご贈答マナー
贈る前に確認しておきたい
ギフトにまつわるマナー集です。
進物の基礎知識
熨斗(のし)
日本の贈り物のルーツは、神に生ぐさもの(魚・肉)を供えたことからきています。贈り物に熨斗を付けるのは、その品物がけがれていないしるしに生ぐさものを添えたのが起こりで、日本人の強いけがれのタブーに起因したものです。古来はあわびの身をそいで干したものを添えており、「肴(さかな)も添えてお贈りします」という意味を表しています。また、昔からあわびは貴重な食材で不老長寿の象徴として用いられました。「のし」とは「のし鮑(あわび)」の略です。現在では「折り熨斗」といって、紅白の紙を雛人形のように折り、その中に短冊型に切った黄色い紙片を包込んでいますが、本来はこの黄色いものがのし鮑です。
慶事には生ぐさものを用いるのがしるしですから、熨斗を付け祝儀の象徴となりました。また、お祝いごとだけでなく、「のし」は「引き伸ばす」の意味から一般贈答にも広く使われるようになりました。逆に弔事(仏教)では、生ぐさものを断つ、引き伸ばしたくないという意味から熨斗は付けません。 尚、鮮魚や肉を贈る場合は、生ぐさが重複するので、熨斗は付けません。その代わり笹の葉を敷きます。現在は中元、歳暮、内祝などで生ぐさものを贈る場合にも熨斗を付けています。
簡単な贈答の時は、よく「のし」という字を書いて代用しますが、これを「わらびのし」といいます。わらびの新芽が出たときの形に似ているので名付けられたものですが、もとは「のし」という字を書いて「ここに熨斗が付いています」という意味に使ったのが起こりです。
熨斗には、宝づくしや飾り熨斗、両折り熨斗や片折り熨斗などがあり、折り込まれ方で、真(しん)、行(ぎょう)、草(そう)、蝶花(ちょうはな)などに分類されますが、どのような時にどれを使用するといった決まりは特にありません。
-

- [飾りのし]
- 婚礼用の飾りのついたのし。
-
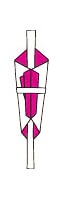
- [両折りのし]
- 慶事一般に使用。
-

- [片折りのし]
- 慶事一般に使用。
-

- [わらびのし]
贈答のマナーしきたりには諸説あり、また各地・各家の伝統やならわしによって異なる場合がございます。
「ご贈答のマナー」は、国内の高島屋各店所在地周辺のしきたりを参考にしています。
掛紙のイラストは、表書きのうち代表的なものを記載しています。
<掛紙>の部分に記載している「のし」とは、のし鮑(折り熨斗)のことを示します。

