![]() MANNERS
MANNERS
高島屋のご贈答マナー
贈る前に確認しておきたい
ギフトにまつわるマナー集です。
弔事
神式
葬儀の香典・供物
仏教と同じですが、香を使わないので香典とはいわず「玉串料」といいます。また、神式では香をたきませんから線香・抹香は使いません。
※神式では「香典」という言葉は使いませんが、ここでは仏式の香典にあたる弔慰金の意味合いで使っています。
[現金を贈る場合]

- 〈金封〉
- のしなし
[東日本] 黒白または双銀5本結び切り
[西日本] 黄白または双銀5本結び切り
- 〈表書き〉
- 御玉串料(おんたまぐしりょう)
御霊前(みたまえ)
御神饌料(ごしんせんりょう)
御供物料(おくもつりょう)
御榊料(おさかきりょう)
姓名を書きます。
※香典袋は蓮の花の印刷されてないものを使用します。
[お供えを贈る場合]
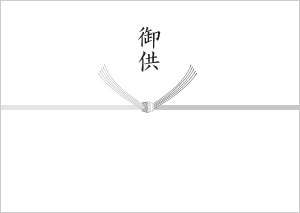
- 〈掛紙〉
- のしなし
[東日本] 黒白5本結び切り
[西日本] 黄白5本結び切り
- 〈表書き〉
- 御供 奉献(ほうけん) 奉納
- 〈好適品〉
- ろうそく 干菓子 最中 果物
鮮魚(海の幸)・野菜(山の幸)・酒などを供えることもあります。
会葬御礼
当日の喪主から引出物を渡します。
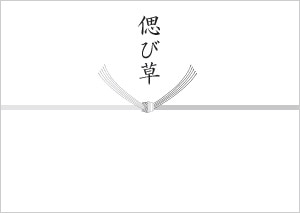
- 〈掛紙〉
- のしなし
[東日本] 黒白5本結び切り
[西日本] 黄白5本結び切り
- 〈表書き〉
- 偲び草 志 偲草 しのび草
- 〈好適品〉
- ハンカチ タオル お茶
霊祭の香典・供物
神式の場合、仏式の法要にあたるものを「霊祭」といいます。
[現金を贈る場合]

- 〈金封〉
- のしなし
[東日本] 黒白または双銀5本結び切り
[西日本] 黄白または双銀5本結び切り
- 〈表書き〉
- 御玉串料 御供料 御榊料(おさかきりょう)
御神前(ごしんぜん)
姓名を書きます。
[品物を贈る場合]
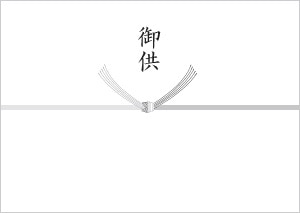
- 〈掛紙〉
- のしなし
[東日本] 黒白5本結び切り
[西日本] 黄白5本結び切り
- 〈表書き〉
- 御供 奉献 奉納
- 〈好適品〉
- 酒・鮮魚(海の幸)・野菜(山の幸)・乾物などを供えることが多いです。
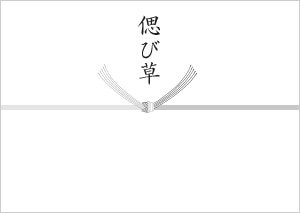
▶お返し
当日の祭主から参列者へ引き物を渡します。
- 〈掛紙〉
- のしなし
[東日本] 黒白5本結び切り
[西日本] 黄白5本結び切り
- 〈表書き〉
- 偲び草 志 偲草
姓のみを書きます。
- 〈好適品〉
- お茶・タオルなどの消耗品
霊祭の香典のお返し
神式では三十日祭または五十日祭を忌明けとして香典返しをします。
本来は香典返しという言葉は仏教のものですが、一般的な慣習として仏式に準じます。
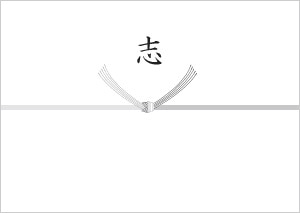
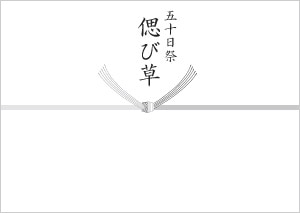
- 〈掛紙〉
- のしなし
[東日本] 黒白5本結び切り
[西日本] 黄白5本結び切り
- 〈表書き〉
- 志 偲び草 偲草(しのびくさ) 五十日祭偲び草
- 〈好適品〉
- タオル・お茶・石鹸などの日用品や消耗品
- 〈不適品〉
- 置物 おめでたいものに通じるもの
豆知識
神式の通夜祭から霊祭の流れは以下の通りです。
| 儀式 | 遺族 | 参列者 | |
|---|---|---|---|
| ご逝去 | |||
| 葬儀 | 通夜祭 葬場祭(葬儀) |
会葬御礼 通夜ぶるまい 精進落とし 葬儀の手伝いへのお礼 |
参列(香典・お供え) |
| 霊祭 | 翌日祭(葬場祭の翌日) 十日祭(ご逝去から10日目) 二十日祭(ご逝去から20日目) 三十日祭(ご逝去から30日目) 四十日祭(ご逝去から40日目) 五十日祭(ご逝去から50日目) 百日祭(ご逝去から100日目) 一年祭(ご逝去から1年目) 三年祭(ご逝去から3年目) 五年祭(ご逝去から5年目) 十年祭(ご逝去から10年目) 二十年祭(ご逝去から20年目) 三十年祭(ご逝去から30年目) 五十年祭(ご逝去から50年目) 百年祭(ご逝去から100年目) |
法要 法要 参列のお礼 香典のお返し |
参列(お供え) |
通夜祭
仏式の通夜にあたる儀式は、神式では「通夜祭」です。仏式の焼香にあたる「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」をします。
玉串は神木である榊(さかき)の枝に木綿(ゆう)や紙を細長く切って下げたもののことです。
直会(通夜ぶるまい)
仏式の通夜ぶるまいに相当する会食を「直会(なおらい)」といいます。宴席を設けて神官や参列者をもてなします。
神式ではけがれは火から移ると考えられているので、喪家で火を用いるのを避けます。
玉串奉奠(たまぐしほうてん)の作法
仏教の「焼香」にあたる儀式を「玉串奉奠」といいます。仏教徒であっても数珠は使用しません。
[神式] 玉串奉奠
 ①
①- 神官から玉串を受けて一礼します。右手で枝、左手で葉を持ち胸の位置に捧げます。祭壇の前に進み出たら喪主・遺族・遺影に一礼します。
 ②
②- 祭壇の2.3歩手前で止まり、玉串を目の高さにして一礼し、祭壇に向かい玉串の技が自分の方に向くように引き寄せます。
 ③
③- 今度は右手で葉先、左手で枝を支えるように持ち替えて、玉串を時計方向に回します。枝の根元を神前に向けて台に供えます。
 ④
④- 二礼二拍手(ただし音は立てない:しのび手という)一礼を行います。
 ⑤
⑤- 数歩下がり、遺族、神官に一礼して席に戻ります。
葬場祭(そうじょうさい)
神式では葬式とはいわず「葬場祭」といいます。これは、神式では故人の霊は、祖先の霊とともに家にとどめ、一家の守護神(氏神)として祭るためです。参列者は仏式と同じと考えてよいでしょう。
霊祭(れいさい)
神式の場合、仏式の法要にあたるものを「霊祭」といいます。
霊祭に招かれた場合は、仏式法要の場合とほとんど同じですが、焼香の代わりに玉串奉奠をします。奉奠の用意がない時は、二礼・二拍手・一礼します。一年祭までは「しのび手」といって、音をたてないで拍手をします。神官のお祓いを受ける時、祭詞奉上(さいしほうじょう)の時はできるだけ深いおじぎをします。
祭礼法要
- < 十日祭 >
- 仏式の初七日にあたります。
本来は、墓前で行いますが、埋葬が済んでいない場合は神職に来てもらい、近親者・友人・知人、葬儀の時にお世話になった方々を招いて祭壇の前で祭祀(さいし)を行います。
- < 五十日祭 >
- 仏式の四十九日にあたり、忌明けとなります。霊祭のなかでも最も重視されます。
葬儀の時に玉串料をいただいたところには忌明けの挨拶をします。最近は五十日祭に「清祓(きよはらい)の儀」と「合祀(ごうし)祭」を一緒に行うことが多くなりました。
贈答のマナーしきたりには諸説あり、また各地・各家の伝統やならわしによって異なる場合がございます。
「ご贈答のマナー」は、国内の高島屋各店所在地周辺のしきたりを参考にしています。
掛紙のイラストは、表書きのうち代表的なものを記載しています。
<掛紙>の部分に記載している「のし」とは、のし鮑(折り熨斗)のことを示します。

