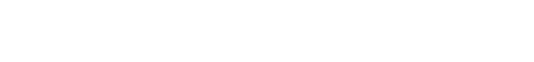
コレクション


キルタ(後のティーマ)
カイ・フランク
1951
アラビア
「キルタ」はフィンランド語で「ギルド(同業組合)」の意。スタッキング可能な用途を限定しない器で、好きな色・器を組み合わせることができるため、フィンランド国内のみならず海外でも広く人気を博した。誰であっても、どのようにでも使うことができるユニバーサルな器である「キルタ」は北欧の機能主義デザインの偉大な到達点である。

ボーレ
タピオ・ヴィルカラ
1967
ヴェニーニ
「bolle」はイタリア語で「泡」の意。イタリアのガラスメーカー「ヴェニーニ」のためにデザインされた本シリーズは、別々に吹いたガラスをひとつに合わせて成形するインカルモ技法で制作されている。ヴェネツィアングラス職人の非常に高度な技がヴィルカラの鋭い色彩・造形感覚と融合し、まさに同じものがふたつとないユニークネスとデザイン性に富んだモダンなアートピースとなっている。

オルキディア(蘭)
ティモ・サルパネヴァ
1954
イッタラ
重量感のある手吹きガラスのフォルムの中央に、湿らせた棒を差し込んで蒸気を発生させて空洞を作る手法がとられている。1954年のミラノ・トリエンナーレでグランプリを受賞し、アメリカのインテリア雑誌『ハウスビューティフル』の「世界でもっとも美しいオブジェ」に選出された。サルパネヴァのアートピースの代表作である。

カンチレヴァーチェア No.21
アルヴァ・アアルト
1931-32
フィンマル
ドイツのバウハウスでスチールパイプ製のカンチレヴァー(片持ち)構造が考案されたのは1926~27年頃である。アアルトもその影響を受けて1929~30年頃には同様の構造の椅子を発表している。しかし、北欧の中にあって金属を椅子に使うことの抵抗感は否めず、木製による構造としたのである。脚の部分は薄板を同じ木目方向に重ねて曲げるラメラ曲げの技術が採用されている。

サヴォイベース
アルヴァ・アアルト
1936
イッタラ
1936年のカルフラ-イッタラガラス製作所主催のコンペティションで優勝した花瓶で、フィンランドデザインを代表する製品のひとつとなった。湖を想起させる緩やかな曲線が当時非常に斬新であったが、翌年のパリ万国博覧会ではスケッチのメモに従って「エスキモー女性の革パンツ」として展示された。今日では内装を担当したレストラン「サヴォイ」にちなんで「サヴォイ」の花瓶とよばれている。

チーフティンチェア
フィン・ユール
1949
ニールス・ヴォッダー
この椅子が1949年、キャビネットメーカーズ・ギルド展に発表された際、デンマーク国王が自ら座られ、「私のためにデザインされた椅子のようだ」との感想を述べられ、ユールは〈キングスチェア〉のネーミングを考えたが恐れ多く、〈チーフティンチェア〉とした。ニールス・ヴォッダー工房では78脚が作られたが、ブラジリアン・ローズウッド材を使ったものは、この作品を含め僅か5脚のみであった。

ザ・チェア プロトタイプ
ハンス J・ウェグナー
1949
ヨハネス・ハンセン
ウェグナー作品の中で最高傑作のひとつだ。その審美性、機能性などあらゆる点において最も高い完成度を示す作品だ。1949年、初めて発表された時にはラウンドチェア(笠木が上から見ると丸いこと)としてあまり話題にならなかった。しかし、アメリカの『インテリアーズ』の1950年2月号で1ページを割いて紹介されるや一夜にして有名になった。また1960年アメリカCBSテレビでニクソンとケネディの討論の場でこの椅子が使われさらに評価を高めた。ザ・チェアという名前はコペンハーゲンのインテリアショップの役員を務めていたアスガー・フィッシャー(Asger Fisher)により命名された。初号モデルでは背に籐を巻き、中の安価なパイン材を隠している。その後、フィンガージョイント工法が採用され、隠すジョイントから見せるジョイントに変わったエポックメーキングな椅子である。

ピーコックチェア
ハンス J・ウェグナー
1947
ヨハネス・ハンセン
背の形が孔雀の羽を広げたように見えるところから“ピーコックチェア”と呼ばれている。この“ピーコックチェア”の名は、彼の友人でもありライバルでもあったフィン・ユールが付けたものである。この椅子のルーツはイギリスのウィンザーチェアにある。スピンドルを放射状に配置し、大きく湾曲した曲木のフレームなど、伝統的なスタイルを踏襲しつつもリデザインによってモダンなデニッシュデザインへと昇華している。

ドルフィンチェア
ハンス J・ウェグナー
1950
ヨハネス・ハンセン
この作品の前年に発表したフォールディングチェアのリデザインモデルである。このドルフィンチェアにはシェーズロングタイプもデザインされていた。いずれも熟練工ならではの美しい仕上げであり、この頃がヨハネス・ハンセン社の黄金期ともいえる。この作品では肘も折り畳むことが可能で、そのメカニズムにもウェグナーの才能が窺われる。30年程前、デンマークの椅子のオークション落札額の記録を書き換えた椅子である。

トルン
イェンス・クイストゴー
1959年
ダンスク・インターナショナル・デザイン
クイストゴーは多くのカトラリーを発表している。その最初のシリーズとしては1947年に発表された〈シャンパンシリーズ〉がある。その後、〈フィヨルド〉や〈オーディン〉など北欧にゆかりのあるシリーズがデザインされた。このトルンはスウェーデンの島の名前(スウェーデン語の発音ではチョルン)からのネーミングである。世界で最も美しいカトラリーではないだろうか。ディナーナイフの先端半分はステンレススチールである。実際に使ってみると、このナイフは決して使い易いものではない。美しさと機能性の両立は難しいようだ。

チークボウル
イェンス・クイストゴー
1956-61
ダンスク・インターナショナル・デザイン
デンマークで大戦後、チーク材が使われ始めたが、そのチーク材に着目したのがフィン・ユールだといわれている。チーク材は木目が目立たないため家具材としてデンマークでは大いに使われた。そのためデンマーク家具はチークスタイルと呼ばれることもあった。チーク材は主にタイ産のものが使われたが、その背景にはデンマーク王室とタイ王室との友交的な関係があった。現在では良質なチーク材が枯渇し、その入手は困難なものとなっている。チーク材をボウルなどに使う場合、一木の無垢材から削り出すためには、乾燥と削り出しを操り返すため、その加工には材料の無駄と時間がかかる。多くの場合、一定の大きさの材を寄せ木としたものを加工している。イェンス・クイストゴーの作品も寄せ木を加工したものだ。

アカデミー・キャビネット
ポール・ケアホルム
1955
ルッド・ラスムッセン
王立芸術アカデミーのためにデザインされたもので、アカデミー・デスクとセットのデザインと考えられる。アカデミー・デスクには小さな引き出しが付いているが同様のプロフェッサーデスクには無い。これらのシリーズはケアホルムの哲学ともいえる“Less is more”の考え方が見事に具現化されている。この作品はルッド・ラスムッセン社で制作された最後の1台である。

イージーチェア
ベント・ヴィンゲ
1958-59
自身の工房
肘掛けが角を連想させる特徴的なデザインだ。この椅子とよく似たデザインは1950年、デンマークのボーエ・モーエンセンがハンティングチェアとして発表。また、イタリアのカルロ・モッリーも同様のデザインを1954年に発表している。モッリーの作品は背の角度を何段階か変えることができるもの。このヴィンゲの作品は、フレームは同様であるがシートを取り外すことができるうえ、角度も自由な位置に設定できる。

キャビネット
ヨーゼフ・フランク
1952
スヴェンスク・テン
フランクの代表作で“ナショナルミュージアム・キャビネット”と呼ばれているもの。明らかに「富裕層のための様式」と言われたアールデコスタイルのデザインである。フランクのデザインした家具には引き出しの取手などに、日本の箪笥を想わせる金具が用いられているが、それはジャポニズムの影響からではないだろうか。

ライオン
カイ・ボイスン
1960年代
カイ・ボイスン
極めて珍しいボイスンの動物シリーズ、麻縄のライオンである。ボイスンといえばモンキーが有名であるが、いずれの作品も子供のみならず、大人の感性で見ても素晴しいものである。ボイスンは動物シリーズではチークやオーク、ビーチ、メープルなど、種々の樹種を見事に使い分け、動物の表現に採り入れた。素材のみならず、そのフォルムもそれぞれの動物の特徴をうまく捉え、デフォルメしている。20世紀のデザイン史に残る名品群である。

エイスタイン-サガ
エイスタイン・サンドネス
1970
ポルシュグルン
1886年創業のノルウェーの陶器メーカー「ポルシュグルン」でアートディレクターであったサンドネスによってデザインされた実用的な陶製食器セット。淡いコバルトブルーと淡いグレー、ブラウンの鉄釉という三色のみの装飾は、簡素でありつつ気品を感じさせる。また注ぎ口や把手の形、大きなつまみといったディティールには機能性へのこだわりが見てとれる。「ポルシュグルン」を代表する名作のひとつ。

プレート
ビルゲル・カイピアイネン
1960年代
アラビア
カイピアイネンは食器デザインも手掛け、また本作のようなアートピースも数多く手掛けた。本作は大皿形の陶板に時計や薔薇といったカイピアイネンの好んだモチーフを配し、鮮やかな釉色と時計の鎖や花の雄蕊を表現した粒状の装飾が目を惹きつける。ビザンチン美術やイタリア・ルネッサンス芸術への傾倒から生まれたカイピアイネンのファンタジックで物語性に富んだ世界観と表現の個性は、北欧モダンデザインの装飾的な一面を体現している。

ボウル
グンナル・ニールンド
1940~60年代
ロールストランド
ニールンドはスウェーデン人の父とデンマーク人の母(陶芸家)の下に生まれ、デンマークとスウェーデンの製陶所でアートピースを制作していたため、デンマーク陶芸とスウェーデン陶芸両方の特徴を備えている。フォルムは幅広い国のやきものから発想しており、色釉を重ね掛けして複雑な斑模様を生じさせる実験性はデンマーク陶芸で培った感性であり、マット釉で処理するクリアなデザイン性はスウェーデン陶芸のそれである。
ODA COLLECTION
椅子研究家の織田憲嗣氏が長年かけて収集、研究してきた、20世紀のすぐれたデザインの家具と日用品群。その種類は北欧を中心とした椅子やテーブルから照明、食器やカトラリー、木製のおもちゃまで多岐にわたり、さらに写真や図面、文献などの資料を含め系統立てて集積されており、近代デザイン史の変遷を俯瞰できる学術的にも極めて貴重な資料で、本展は、織田コレクションをもとに会場を構成しています。


(c) Kentauros Yasunaga
織田憲嗣(のりつぐ) プロフィール
椅子研究家・東海大学名誉教授・東川町文化芸術コーディネーター。
1946年高知県生まれ。大阪芸術大学卒業後、高島屋宣伝部にイラストレーター、グラフィックデザイナーとして勤務。その後独立しデザイン事務所を設立。1994年から北海道東海大学芸術工学部(当時)教授となり、特任教授を経て2015年まで務めたのち現職に。現在北海道東神楽町の森の中の自邸で暮らす。
